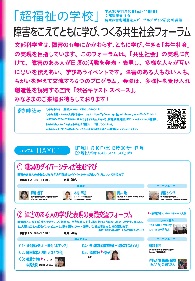平成30年度「超福祉の学校 ~障害をこえてともに学び、つくる共生社会フォーラム~」開催報告
文部科学省は、障害の有無にかかわらず、共に学び、生きる「共生社会」の実現を目指しています。
平成30年11月10日(土曜日)、11日(日曜日)に、東京都渋谷区の「SHIBUYA CAST./渋谷キャスト」ほかにて、NPO法人ピープルデザイン研究所との共催で本フォーラムを開催しました。
2日間にわたる延べ6つのプログラムには、延べ400名を超える参加があり、共生社会の実現に向けて、幅広い方々が学びあう機会になりました。
この度、その記録映像が完成しました。ぜひ以下のリンクより御覧ください。
※「超福祉の学校2019」については、こちらをご覧ください。
記録映像
※以下の映像において、2021年1月7日から2月3日までの間、『「超福祉の学校」障害をこえてともに学び、つくる共生社会フォーラム』ではない動画が掲載されておりました。訂正し、期間中に当該サイトをご覧になり、動画を視聴された方々に、お詫び申し上げます。
「超福祉の学校」障害をこえてともに学び、つくる共生社会フォーラム(※「YouTube」文部科学省動画チャンネルへリンク)
映像の構成
『「超福祉の学校」障害をこえてともに学び、つくる共生社会フォーラム』(約30分)
開催趣旨 冒頭~
プログラム1「職場のダイバーシティが生む学び」 1分50秒頃~
プログラム2「障害のある人の学びと表現の実践交流フォーラム」 6分45秒頃~
プログラム3「みんなでつくる!バリアフリーマップ」 9分35秒頃~
プログラム4「自閉症VR体験ワークショップ」 12分25分頃~
プログラム5「平成まぜこぜ一座 パフォーマンス『プチ月夜のからくりハウス』」 16分00分頃~
プログラム6「MAZEKOZE トーク『生きづらさダヨ!全員集合~!』」 16分40秒頃~
「超福祉の学校~障害をこえてともに学び、つくる共生社会フォーラム~」チラシ
開催概要
1.開催期間
平成30年11月10日(土曜日)、11日(日曜日)
2.会場
渋谷キャスト スペース(G階)、渋谷ヒカリエ8階 8/ COURT
渋谷キャストアクセス(※外部サイト:渋谷キャストホームページへリンク)
渋谷ヒカリエアクセス(※外部サイト:渋谷ヒカリエホームページへリンク)
3.主催等
主催:文部科学省
共催:特定非営利活動法人ピープルデザイン研究所
協力:一般社団法人Get in Touch、富士通株式会社、富士通デザイン株式会社、株式会社ソーシアルサイエンスラボラトリ
※「2020年、渋谷。超福祉の日常を体験しよう展」(通称:超福祉展)との連動企画
超福祉展について(※外部サイト:超福祉展ホームページへリンク)
渋谷区内の複数会場にて、平成30年11月7日(水曜日)~13日(火曜日)に開催される特定非営利活動法人ピープルデザイン研究所主催のイベント。
プログラム
【1日目】11月10日(土曜日)12時30分~17時00分
1. 職場のダイバーシティが生む学び
- 内容:障害のある人の多様なはたらき方や職場のダイバーシティが生む学びについて考えます。
- 時間:12時30分~14時00分
- 会場:渋谷キャスト スペース(G階)
- 定員:90名
- 登壇者:
○コーディネーター:須藤シンジ(特定非営利活動法人ピープルデザイン研究所)
○パネリスト:
・箕輪優子(橫河電機株式会社 人財総務本部室ダイバーシティ推進課)
・木村幸絵(ソフトバンク株式会社 CSR統括部CSR部)
・岡井敏(株式会社ゼネラルパートナーズ 取締役副社長)
2. 障害のある人の学びと表現の実践交流フォーラム
- 内容:障害のある方々が、学んできたこと、得意なことを発表します。取り組むようになったきっかけや、楽しいこと、大変なことなどをインタビューし、歌や踊り、アートを通して、参加者みんなで交流します。
- 時間:15時00分~17時00分
- 会場:渋谷キャスト スペース(G階)
- 定員:90名
- 登壇者:
○コーディネーター:
・浦野耕司(渋谷区知的障害者幡ヶ谷教室「GAYA」運営委員長)
・渋谷区知的障害者幡ヶ谷教室「GAYA」のみなさん
○発表者:
1.社会福祉法人 一麦会「ポズック」
2.町田市本人活動「とびたつ会」
3.横溝さやか(アーティスト、文部科学省スペシャルサポート大使)、
中尾大良(studio COOCA)
4.渋谷区知的障害者幡ヶ谷教室「GAYA」
5.金澤翔子(書家、文部科学省スペシャルサポート大使) ・金澤泰子(書家)
○アート協力:The Blue Love by sense+KAZ
※協力:株式会社富士通ソーシアルサイエンスラボラトリ
【2日目】【日時】11月11日(日曜日)12時00分~19時00分
3. みんなでつくる!バリアフリーマップ
- 内容:スマホ等でバリアフリー情報をシェアできるアプリ「WheeLog!」を活用した体験型ワークショップです。
- 時間:12時00分~14時00分
- 会場:渋谷キャスト スペース(G階)
- 定員:40名
- 司会:ジョンソン(舞台役者)
- 講師:
・織田友理子(みんなでつくるバリアフリーマップCEO、遠位型ミオパチー患者会代表)
・伊藤史人(WheeLog! CTO、島根大学総合理工学部助教)
・吉藤オリィ(WheeLog! CKO、株式会社オリィ研究所所長)
4. 自閉症VR体験ワークショップ
- 内容:バーチャルリアリティ(VR)の教材を活用した自閉症体験プログラムです。
- 協力:富士通株式会社、富士通デザイン株式会社
- 時間:14時30分~16時00分
- 会場:渋谷キャスト スペース(G階)
- 定員:40名
- 講師:
・坂井聡(香川大学教育学部教授 バリアフリー推進室長)
・杉妻謙(富士通デザイン株式会社 サービスインテグレーション・デザイングループ)
※協力:富士通株式会社、富士通デザイン株式会社
5. 平成まぜこぜ一座 パフォーマンス「プチ月夜のからくりハウス」
- 内容:様々な背景のある当事者アーティストによるパフォーマンスです。
※一般社団法人Get in Touchとの協働企画 - 時間:15時00分~15時30分
- 会場:渋谷ヒカリエ8階 8/ COURT
- 定員:40名
- 登壇者:
○座長:
・ 東ちづる(女優、一般社団法人Get in touch代表理事、文部科学省スペシャルサポート大使)
・ホーキング青山(障害者芸人)
○手話:森本行雄
○出演:
・森田かずよ(義足の女優・ダンサー)
・GOMESS(ミュージシャン/自閉症)
・かんばらけんた(車椅子ダンサー)
・名取寛人(バレエダンサー)
・踊るラッキーボーイ想真(発達障害(自閉症)、無性別ダンサー)
6. MAZEKOZE トーク「生きづらさダヨ!全員集合!」
- 内容:生きづらさを感じている様々な背景のある人たちが車座になって、「私のまぜこぜ・生きづらさ」を、ぶっちゃけトーク。 「みんなで一緒に生きる」ために語り合う対話型セッションです。
※一般社団法人Get in Touchとの協働企画 - 時間:17時00分~19時00分
- 会場:渋谷キャスト スペース(G階)
- 定員:90名
- ・登壇者:
○ファシリテーター:東ちづる(女優、一般社団法人Get in touch代表理事、文部科学省スペシャルサポート大使)
○発表者:
・森田かずよ(義足の女優・ダンサー)
・GOMESS(ミュージシャン/自閉症)
・かんばらけんた(車椅子ダンサー)
・名取寛人(バレエダンサー)
・踊るラッキーボーイ想真(発達障害(自閉症)、無性別ダンサー)
○コメンテーター:ホーキング青山(障害者芸人)
○手話:森本行雄、田村梢
○グラフィックファシリテーション:鈴木さよ(株式会社しごと総合研究所)
※その他
- プログラム1~4は音声認識ソフトによる字幕投影を実施。
- プログラム5、6は手話通訳あり。
- 二日間とも渋谷キャストスペース(G階)内にて、「PARK CAFE」による飲物販売を実施。
※ 「スペシャルサポート大使」について (※文部科学省ホームページ内「スペシャルサポート大使」についてウェブサイトへリンク)
文部科学省では、障害の有無にかかわらず、ともに学び、生きる「共生社会」の実現に向けた普及・啓発を図るため、著名人を「スペシャルサポート大使」に任命し、広報活動やイベントへの協力を依頼しています。